ブログ
11.282025
養子にも法定相続権はありますか?
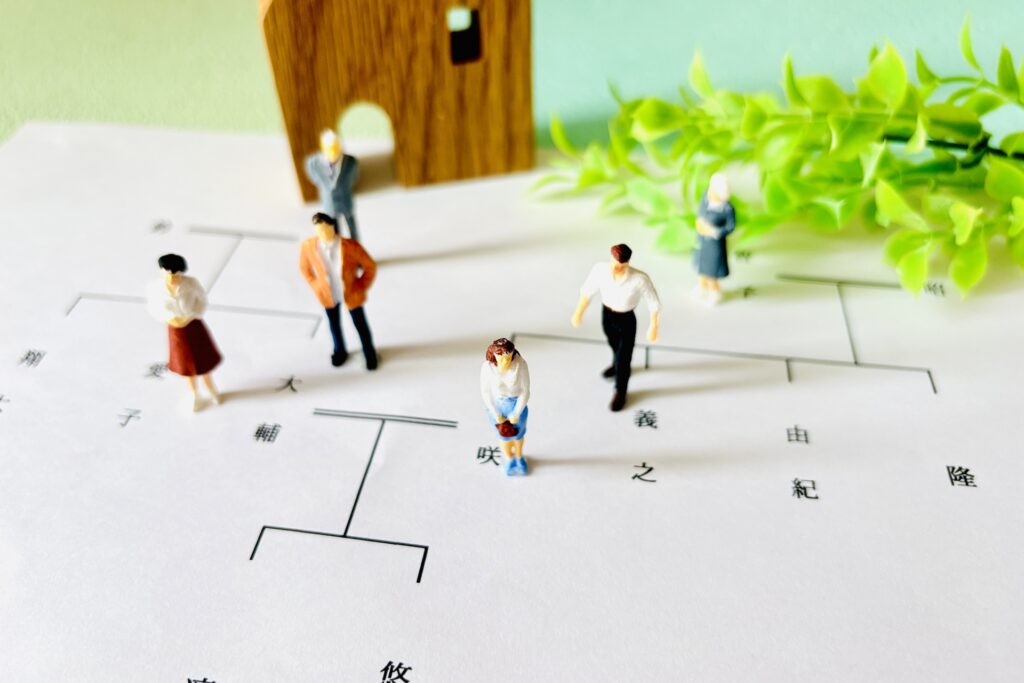
養子の相続権は、相続を考える際に多くの家庭で疑問として挙がるテーマです。
家族の形が多様化する中で、養子縁組が相続にどう影響するのかを正しく理解することは、トラブル防止のために非常に重要です。
養子縁組には種類があり、その違いによって相続関係が変わることもあるため、事前に整理しておくことが望まれます。本記事では、法律上の基本原則と、行政書士が支援し得る範囲を踏まえて、わかりやすく解説します。
1|養子の相続権は法律で明確に定められています
■ 普通養子縁組
・養親との間に法律上の親子関係が成立
・実親との親子関係もそのまま継続
→ 養親側・実親側の双方に相続権が生じる可能性があります(条件による)
■ 特別養子縁組
・養親との親子関係のみに一本化
・実親との法律上の親子関係は終了
→ 相続権は養親側のみ
いずれの場合でも、養子は民法上の「実子」と同じ立場で相続権を持つことが原則です。
2|養子の人数や家族構成で相続は複雑になることも
養子が複数いる場合、法定相続分は実子と同様に平等です。
一方、以下のような要素で手続きが複雑になることがあります。
-
養子縁組の届出が正しく完了していない
-
遺言書がない場合の相続人の範囲の誤認
-
普通養子・特別養子の混在
-
生前贈与の有無
-
不動産相続の分割方法 など
これらは事実関係の整理がとても重要で、戸籍類や縁組記録を正確に確認する必要があります。
3|行政書士が支援できること
行政書士は、相続に関する法律判断や紛争代理は行えません。
そのため以下のような業務が可能です。
■ 行政書士ができるサポート
-
戸籍・養子縁組届など必要書類の収集代行
-
養子縁組の成立状況の確認(戸籍の範囲内)
-
相続関係説明図の作成
-
相続手続きに必要な書類整理
-
遺言書作成のサポート(文案作成・形式チェック)
-
相続人間の話し合いの内容を書面化(遺産分割協議書の作成)
※ただし争いがある場合の調整・仲裁は不可
■ 行政書士ができないこと
-
相続分についての法的判断
-
争いのある遺産分割の交渉や代理
-
遺留分侵害額請求の判断・代理
-
調停・訴訟の代理
紛争の恐れがある場合は、弁護士と連携しながら行政書士は書類面・事実整理面を担当する、という形が適切です。
4|よくある誤解と注意点
✘ 誤解①:養子は遺言がないと相続できない
→ 誤り。養子も法定相続人です。
✘ 誤解②:実子より相続分が少ない
→ 誤り。実子と同等です。
✘ 誤解③:離縁しても元養親を相続できる
→ 誤り。原則として相続権は消滅します。
正しい権利理解はトラブル防止に直結します。
5|トラブルを防ぐために必要な対策
-
養子縁組の届出状況を事前に確認
-
相続が発生する前に戸籍確認を済ませておく
-
生前贈与の記録を整理
-
遺言書を作成しておく(公正証書遺言が推奨)
-
相続発生後は早めに書類整理を開始
特に不動産が絡む場合は分割協議が長引きやすいため、事前準備が有効です。
6|まとめ
養子の相続権は法律で明確に保障されており、実子と同等の扱いを受けます。
ただし、
-
養子縁組の種類
-
戸籍の記載状況
-
遺言の有無
-
生前贈与などの事実
-
不動産があるか否か
によって実務の進め方は大きく変わります。
行政書士は争いがない相続の書類作成や事実関係整理の専門家として、手続き面の負担軽減に貢献できます。
疑問がある場合は早めに相談し、権利行使をスムーズに進める準備をすることが大切です。



