ブログ
11.132025
「数次相続」と「代襲相続」を誤解すると相続人調査が長引く理由
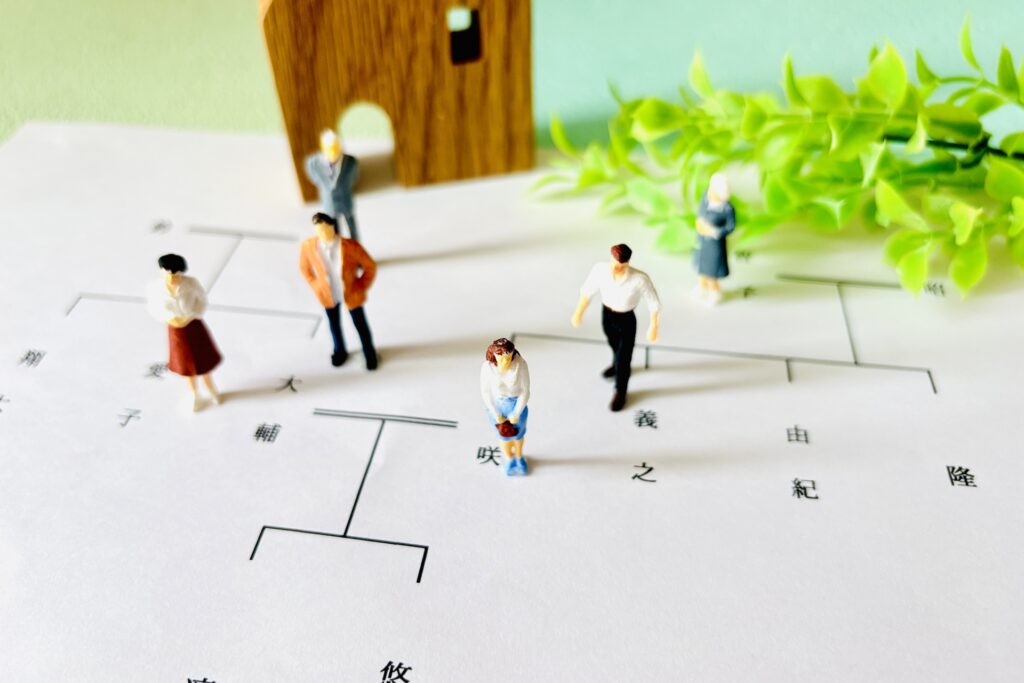
相続の現場では、数次相続と代襲相続という制度がよく問題となりますが、これらを正しく理解せずに手続きを進めると、相続人の調査が長引き、遺産分割協議や相続手続き全体に支障が出ることがあります。
特に、高齢化や家族構成の多様化が進む地域においては、相続人の死亡・転籍・再婚・養子縁組などの事情が絡み、相続人の確定が思わぬ時間を要するケースも増えています。
本記事では、全国対応の相続手続きとして「数次相続」と「代襲相続」の違いや、それぞれ発生しやすいパターン、調査・書類収集において注意すべきポイントを整理します。さらに、行政書士が関われる支援範囲を明示しながら、手続きの長期化を防ぐための実務的なヒントもご紹介します。
■ 数次相続と代襲相続、それぞれの基本
代襲相続とは、被相続人の相続開始時点で、法定相続人となるべき人(例えば子)が既に死亡している場合、その子・孫が「代わりに」相続人となる制度です。
数次相続とは、被相続人の相続開始後に、相続人となった者(例えば子)が、遺産分割や名義変更前にさらに死亡するなどして、次の相続が生じる連続的な相続を指します。
このように、両者は「誰が相続人になるか」「どの時点で死亡しているか」という点で“似て非なる”制度です。
■ なぜ「誤認」すると時間がかかるのか
-
相続人の範囲が拡大・変動することで、戸籍・除籍・改製原戸籍の収集範囲が広がることがある。
-
数次相続の場合、相続手続き前にさらに相続発生という事態を見落とすと、次段階の相続人を後から調査する必要が出る。
-
代襲相続と誤認して手続きを進めると、「配偶者が相続人にならないはず」という認識がずれ、協議対象に含めなかったり、家系図をきちんと整理できなかったりする。
-
情報が古かったり、家族が遠方・疎遠だったりすると、「誰が相続人なのか」「どこまで戸籍を遡るか」が不透明になり、書類収集だけで数ヶ月かかる例もあります。
■ 調査・書類収集の要点
-
被相続人の死亡時から、相続人となり得る者の死亡・続存状況の確認
→ 例えば、被相続人Aの子Bが相続人として確定、その後Bが死亡していた場合、それが数次相続に該当する可能性があります。 -
戸籍・除籍・改製原戸籍の徹底取得
→ 複数転籍・婚姻・養子縁組があると、取得すべき戸籍が複数市町村にまたがることがあります。 -
相続人全員の最新住民票・印鑑証明の収集
→ 遠方居住・海外在住などがあると別途時間がかかるため、早めに着手することが望ましいです。 -
相続関係説明図(家系図)を作成して相続人の権利関係を視覚化
→ 調査途中で「この人が相続人だったかもしれない」という事態を整理しやすくなります。 -
遺産分割協議の場で誰が参加すべきかを速やかに確定する
→ 特に数次相続が関与すると、子ども・孫・配偶者・親族と関係者が増えるため、協議対象の範囲を事前に明確にすることが重要です。
■ 行政書士が支援できる範囲とその限界
行政書士は、相続人調査・書類収集代行・相続関係説明図作成・遺産分割協議書の文案作成支援など、手続きの前段階で大きな役割を果たせます。ただし、例えば登記申請そのもの(不動産名義変更)や家庭裁判所での法定相続人の確定など、司法書士・弁護士等の専権業務については、行政書士の単独代行は適用されないので、必要に応じ適切な専門家への相談・連携が必要です。
■ スムーズに進めるためのポイントまとめ
-
手続きを先送りしない:相続開始後、できるだけ早期に相続人調査を開始することで、数次相続・代襲相続の発生を早期に察知できます。
-
家系・戸籍を可視化する:相続関係説明図を用いて複雑な家系を整理することで、相続人漏れ・誤認を防げます。
-
関係者を早期に確定し、協議へ移る:相続人が多数・複数世代にまたがる場合は、開始前から参加範囲を確認しておくと遺産分割協議が長引きにくくなります。
-
専門家と適切に連携する:行政書士が支援できる範囲と、司法書士・弁護士の登場タイミングを理解しておくことで、無駄な重複作業や費用が抑えられます。
■ よくある質問と簡単な回答
Q1:数次相続と代襲相続の判断ポイントは?
→ 被相続人の相続開始(死亡)時点で、法定相続人となるべき者が既に死亡していれば「代襲相続」、手続き前に相続人が死亡していれば「数次相続」と整理できます。
Q2:調査だけ依頼できますか?
→ はい、行政書士は戸籍収集代行・相続関係説明図作成など、調査段階の支援が可能です。
Q3:相続人を調べた結果、思ったより多かったのですが?
→ 相続人が多くなると協議が長引く可能性があります。家系図整理・説明図作成・代理人調整支援など、早期に専門家活用が効果的です。
■ まとめ
数次相続・代襲相続の制度を正しく理解し、相続人の調査を早期に着手することで、遺産分割協議・相続手続きの長期化を防ぐことができます。行政書士の支援を上手に活用しつつ、必要に応じて司法書士・弁護士とも連携することで、安心して手続きを進められます。相続開始後、できるだけ早く調査と合意形成を始めることが、トラブル回避への第一歩です。



