ブログ
11.212025
兄弟姉妹にも相続権がありますか? ――法定相続人の順位と実務上の注意点
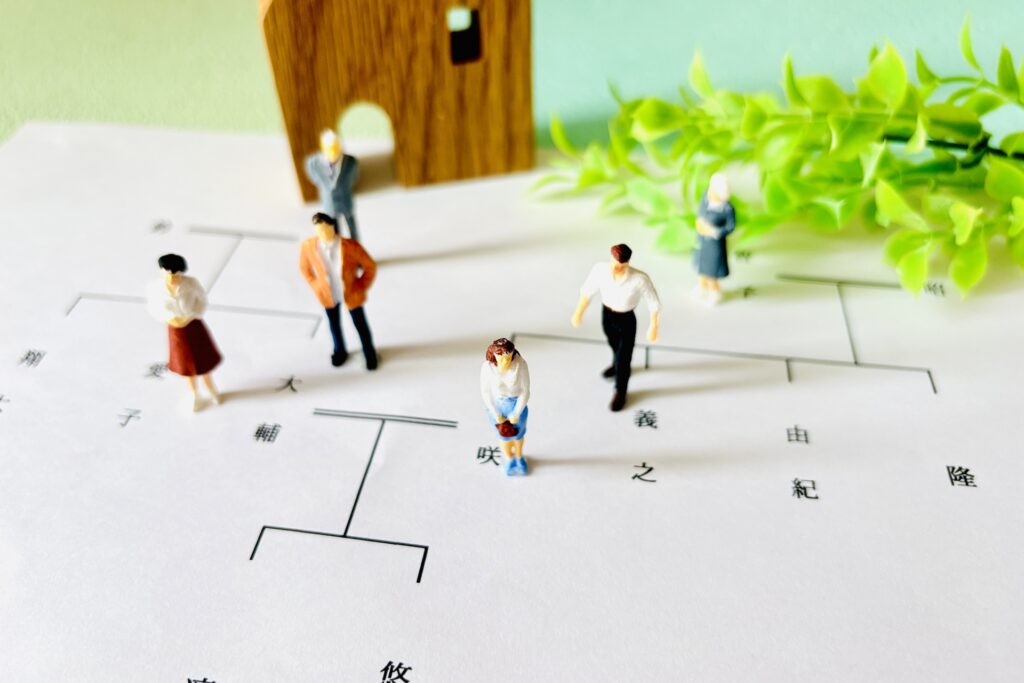
相続のご相談でとても多いのが、
「兄弟姉妹にも相続権はあるんですか?」
というご質問です。
「子どもがいないから全部配偶者だと思っていた」
「兄弟だから口を出さない方がいいと思っていた」
といった“思い込み”のまま話を進めてしまうと、
後から「そんなつもりではなかった」というトラブルになりかねません。
この記事では、地域を問わず共通する 兄弟姉妹の相続権の基本 と、
実務上の注意点・専門家に相談するタイミングを、
行政書士の立場からわかりやすく整理します。
(※内容は日本の民法に基づく一般的な解説であり、
紛争の個別判断や訴訟・調停の代理を行うものではありません)
1.兄弟姉妹は「第3順位」の法定相続人です
民法上、法定相続人の順位は次のとおりです。
-
子(および代襲相続する孫など)
-
直系尊属(父母・祖父母など)
-
兄弟姉妹
※いずれの場合も、配偶者は常に相続人になります。
したがって、兄弟姉妹に相続権が出てくるのは、
-
被相続人に
-
配偶者も子もおらず
-
直系尊属(父母・祖父母)もすでに亡くなっている
といったケースです。
-
全血と半血の兄弟姉妹
-
父母がどちらも同じ…全血兄弟姉妹
-
片方の親だけ同じ…半血兄弟姉妹
法定相続分は、
-
全血兄弟姉妹:基準の相続分
-
半血兄弟姉妹:全血の1/2
となります(人数が複数いれば、その中で按分)。
この「半血の相続分」を知らずに話し合いを続けてしまうと、
「不公平だ」「軽く扱われた」といった感情の対立を生みやすいため、
まずは法定相続分の仕組みを全員で共有することが重要です。
2.よくある勘違いと、こじれやすいパターン
兄弟姉妹が相続に関わる場面では、次のような誤解がよく見られます。
① 「兄弟には相続権がない」と思い込んでいる
-
「子どもがいないから、全部配偶者だと思っていた」
-
「兄弟は“遠い親族”だから相続人にならないと思っていた」
実際には、
配偶者・子・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
「自分には権利がない」と思い込んで手続きから外れてしまうと、
後から権利主張が出てきてやり直し、ということもあり得ます。
② 遺言書の有無を確認しないまま話し合いを始める
-
遺言書があれば、基本的にはその内容が優先
-
兄弟姉妹が相続人にならない内容の遺言がある可能性もある
にもかかわらず、
遺言書の確認をせずに「法定相続分前提」で話を進めてしまい、
後から公正証書遺言が見つかるというケースもあります。
③ 半血兄弟姉妹の取扱いを知らない
「なぜ自分だけ相続分が少ないのか」を法律の問題ではなく
“扱いの問題”だと感じてしまい、感情的な対立になることがあります。
法的な仕組みを冷静に共有することが大切です。
3.兄弟姉妹が相続人になるときの実務上の注意点
(1)まずは「相続人の範囲」と「遺言書の有無」を確認
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、
子・直系尊属・兄弟姉妹、代襲相続人などを確認 -
自筆証書遺言・公正証書遺言がないかも確認
行政書士は、戸籍収集や相続関係説明図の作成など、
相続人調査に関する書類作成・整理のサポートを行うことができます。
(2)相続放棄の期限に注意
-
相続放棄・限定承認は、原則として
**「相続があったことを知った日から3か月以内」**に家庭裁判所へ申述が必要です。 -
借金が多い可能性がある場合は、早めに情報収集を。
※家庭裁判所の手続きや可否判断、紛争性のある案件などは、
弁護士等への相談が適切です。
行政書士は、
-
資料整理
-
事実関係の整理メモ作成
-
期限管理の助言
といった“準備部分”でお手伝いする立場になります。
(3)遺産分割協議は「全員参加」と「書面化」が基本
兄弟姉妹が相続人になる場合、
普段なかなか会わない関係のことも多く、
感情的なすれ違いが起こりやすい場面です。
-
相続人全員が参加した協議であること
-
まとまった内容は遺産分割協議書として書面に残すこと
がとても重要です。
行政書士は、
-
遺産分割協議書の案文作成
-
相続関係説明図や財産目録の作成
といった「書類作成」の面から、
当事者の話し合いをスムーズに進めるためのサポートができます。
※相続人同士の対立が激しい場合や、代理交渉・調停・訴訟が必要な場合には、
弁護士の領域となりますので、弁護士への相談・紹介が必要です。
4.行政書士に依頼できること・できないこと
業際(業務の境界)に関する不安をお持ちの方も多いので、
兄弟姉妹の相続に関して、行政書士の支援範囲を整理しておきます。
■ 行政書士がお手伝いできること(例)
-
相続人調査に必要な戸籍等の収集・整理
-
相続関係説明図・財産目録の作成
-
遺産分割協議書の作成
-
自筆証書遺言の文案作成サポート(形式面の助言など)
-
手続きの流れや必要書類に関する一般的な説明
-
他士業(司法書士・税理士・弁護士など)への紹介・連携
■ 行政書士が行えないこと(他士業の専門分野)
-
紛争事件についての代理交渉・調停・訴訟対応(→弁護士)
-
相続登記の申請代理(→司法書士)
-
相続税の申告や具体的な節税アドバイス(→税理士)
-
家庭裁判所での手続きにおける代理人としての関与(→弁護士 等)
兄弟姉妹間の相続で
「今どこまで誰に頼めるのか分からない」と感じた場合は、
まず行政書士などに相談し、
必要に応じて他士業と連携してもらう形が安心です。
5.まとめ
-
兄弟姉妹にも、条件を満たせば法定相続人としての相続権がある
-
配偶者・子・直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹の相続権が問題になりやすい
-
全血と半血で相続分が違うため、法的な仕組みの共有が重要
-
遺言書の有無、相続放棄の期限、相続人の範囲の確認は「最初の必須ステップ」
-
行政書士は、書類作成・情報整理・他士業との連携といった
“手続き面のサポート役”として活用できる
兄弟姉妹が相続人となるケースは、
法律と感情が絡み合いやすく、
「早めに事実関係を整理し、書面を整えておくこと」が何よりの予防策です。
自分たちだけで進めるのが不安な場合は、
相続を多く扱う行政書士や、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士など、
それぞれの専門家に早めに相談することをおすすめします。



